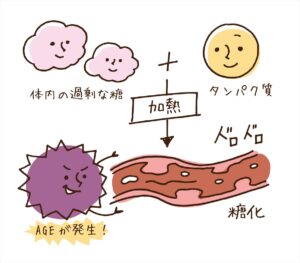「食生活アドバイザーは意味ない」
「食生活アドバイザーは役に立たない」
などの書き込みを見て、資格の取得に悩んでいませんか?
結論から言うと、食生活アドバイザーは「就職のために資格を求める人」からすると無駄に見えることもあります。しかし、日常生活で健康管理に生かしたい、食について詳しくなりたいという人が目標として取るにはとても有用な資格です。
この記事では、食生活アドバイザーをとるメリット・デメリットについて就職・生活面から詳しく解説していきます。
ほかの「食」に関する資格比較も紹介しますので、食についての知識を深めたい方、どの資格をとろうか悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。
食生活アドバイザーとは?
『食生活アドバイザー』は、広い視野に立って食生活をトータルにとらえ、健康な生活を送るための提案ができる”食生活全般のスペシャリスト”です。
食文化から栄養学や食品学、衛生管理などの栄養の専門知識と「食品を買うときの賢い食材の選び方」や、「食にまつわる経済や社会の仕組み」まで幅広い分野を学ぶことができます。

食にまつわる幅広い知識を習得することで、「食を通して健康的な生活を送りたい」、「食品安全など正しい情報か判断できる人になりたい」、「賢く買い物したい」と思う気持ちをサポートしています。
食生活アドバイザー資格が無駄と言われる理由は?評判・口コミを調査
「食生活アドバイザー」とネットで検索すると、「食生活アドバイザー 無駄」とでてくるので少し心配になりますよね。口コミでも、そのような意見もみられます。
食生活アドバイザーが無駄と言われる理由は3つ。
- 民間資格で難易度が低い
- 就職に役立ちにくい
- 知識問題だけなので忘れやすい
それぞれについて詳しく解説していきます。
民間資格で受験難易度はひくい
食生活アドバイザーは一般社団法人 FLAネットワーク協会が主催する民間資格。国が法律で定めている国家資格とは違い、民間団体が資格試験を実施しています。
受験資格は必要なく、申し込めば年齢・国籍問わず誰でも受験することができるため「だれでも簡単に資格がとれる」と思われがち。しかし、実際の食生活アドバイザー2級の合格率は約30%。ちゃんと勉強して知識を得ないと取得は難しい資格です。
口コミでも「意外とむずかしい」との意見もありました。
就職に役立ちにくい
食生活アドバイザーは独占資格(資格者以外が業務に携われない資格)ではありません。調理師や管理栄養士のように「食生活アドバイザー」という職業はなく、この資格が無いとできない仕事はないのです。
肩書きを気にする方は、食生活アドバイザーとして就職できなければ「無駄」と思うかもしれません。しかし「食生活アドバイザー=”食”に詳しい人」であるということは変わらない事実です。
食にまつわる知識が豊富なので、調理師や管理栄養士とは異なる分野でも活躍することができる可能性もありますよ。
知識問題だけなので忘れやすい
食生活アドバイザー試験は、マークシート形式、記述式で全て知識を問われる試験です。決まった出題範囲からマークシートの選択式、最近のニュースに関連した記述式の問題が出されます。
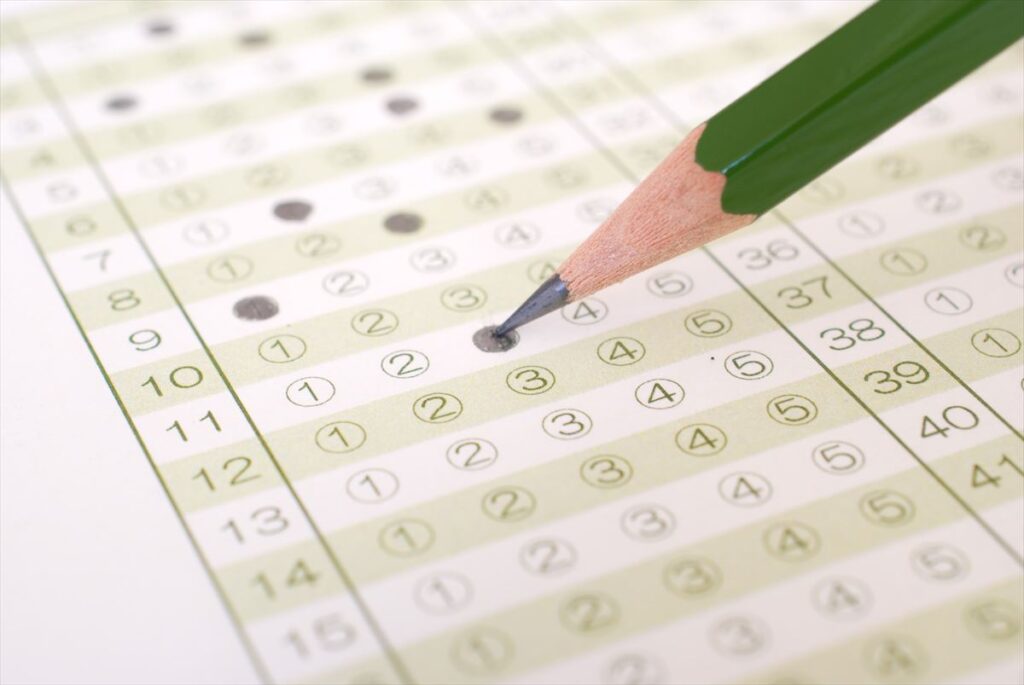
実務試験などがないため手軽に受験できる一方、習得した知識を使わないと忘れてしまう可能性も。
ただ、どんな資格も取っただけでは忘れてしまいます。習得した知識を日常生活の中でも活用し、定着させると自分のためにもなりますよ。
食生活アドバイザーをとるメリット・デメリット|就職・生活面に役立つ?
無駄と思われていた食生活アドバイザーの資格ですが、実は取得することで役に立つこともたくさん!ここではメリットとデメリットについて解説していきます。
メリット
食生活アドバイザーをとったときのメリットは5つです。
- 正しい食生活が送れることで健康寿命をのばし、生活習慣病リスクを低減できる
- 栄養の知識がついて正しいダイエット方法がわかる
- スーパーなどでかしこく食品を選べる
- 食材を無駄にしない食品保存で環境にも配慮できる
- 食文化や伝統的な風習が学べることで教養が身に付く
正しい食生活を送ることは健康寿命を伸ばすことにつながります。健康寿命とは、2000年にWHOが定めた「日常生活が制限されることなく健康に生活できる期間」のこと。今の日本では平均寿命と健康寿命の差は男性で9年、女性で12年間。
このままでは、10年近くも体に不調をかかえながら過ごし、周りの家族にも介護で負担を強いることになってしまいます。
日本人の死因の約6割は生活習慣病です。食生活を見直して生活習慣病のリスクを下げることで健康寿命を伸ばすことは、自分も家族も長い人生でとても大きなメリットになりますよ。

また、世間ではいろんなダイエット方法が溢れています。専門家でもない方がSNSやYoutubeで発信する情報の中には、誤った情報が拡散されている場合も。食の知識がないと、ぜんぶ鵜吞みにして誤ったダイエットを行い、からだを壊すリスクもあります。
自分の体にあったダイエットとは何か、どの栄養素をとる必要があるか、食の知識があれば簡単に見極めることができますよ。
そのほか、食品表示の知識も増えるので「無添加」表示に惑わされずにかしこい食品選びにも役立ちます。食材の最適な保存方法を知ることで、食品ロスを減らしてSDGsにも貢献できますよ。
日本の伝統的な食文化やハレの日の料理・風習も学べます。教養が身につくことで、大切な場面でも恥ずかしくない振る舞いが自然とできますね。
デメリット
食生活アドバイザーを取得するデメリットは強いて言うなら2つ。
- 単体では職業にならない
- 1つの分野の専門性を極められない
「無駄といわれる理由」でも述べたように、食生活アドバイザー単体では職業になりません。資格をとってそれを職業としたい人にはデメリットと感じるとこもあるでしょう。
ただし、食の知識をもっていることはアピールできます。飲食店のスタッフやスーパーの販売員の就職活動に活かせたケースも。食育を生かしたメニュー提案や、お客さんに食材オススメの保存方法を教えるなど、食の知識があると活躍の場が広がりますよ!

また、食生活アドバイザーは栄養学だけでなく食習慣や食品物流など食に関わる多くの分野を学びます。1つの分野の深掘りまではできないので、「栄養学に特化して学びたい」人には物足りない可能性も。
ただし食生活アドバイザーの勉強をすることで、「食」について知る良いきっかけになります。勉強しながら興味をもった分野を自分で改めて知識をつけるのもアリですね。
「食」に関する資格を徹底比較!
日本に食にまつわる資格は多数ありますが、中でも人気の高い資格を比較してみました。
| 食生活アドバイザー | 管理栄養士 | 調理師 | 食育インストラクター | フードアナリスト | 野菜ソムリエ | |
| 資格の種類 | 民間資格 | 国家資格 | 国家資格 | 民間資格 | 民間資格 | 民間資格 |
| 受験資格 | だれでも受験可能 | ・管理栄養士養成施設卒業 ・栄養士として1〜3年実務以上の実務経験 | ・調理師学校卒業 ・飲食店で2年以上調理経験 | 通信講座「服部幸應の食育インストラクター養成講座」を受講 | だれでも受験可能 | 認定協会主催の講座(通信または通学)を受講 |
| 実技の有無 | なし | なし | なし | なし | 味覚試験あり | なし |
食生活アドバイザーは誰でも受験でき、実技試験もないので気軽に食の知識をつけたい方にオススメの資格です。
食生活アドバイザーの資格情報を詳しく解説
食生活アドバイザーはユーキャンの20.30代女性人気講座ランキングでも3位になるほど人気の資格。
1999年に制定された食生活アドバイザーは受験者数も年々増え、2022年の受験者数は2級、3級合わせて1万人にものぼります。
それぞれの合格率は2級30.8%、3級59.8%(2022年6月検定実績)。2級は時事問題もあり難易度があがりますが、3級は出題範囲をしっかり勉強すれば確実に合格できる資格です。
出題科目は、2級、3級ともに以下の6項目。
●栄養と健康(栄養・病気予防・ダイエット・運動・休養など)
●食文化と食習慣(行事食・旬・マナー・配膳・調理・献立など)
●食品学(食材・加工食品・有機食品・食品表示・安全性・環境問題など)
●衛生管理(食中毒・衛生管理・予防・食品化学など)
●食マーケット(流通・物流・外食・メニューメイキング・食品販売など)
●社会生活(消費経済・生活環境・消費者問題・IT社会・関連法規など)
受験情報はこちら。
| 受験資格 | 年齢・国籍を問わずだれでも受験可能 |
| 受験日程 | 毎年6月と11月 |
| 試験会場 | 札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡 |
| 出題形式 | 3級:選択問題(マークシート) 2級:選択問題(マークシート)、記述式問題(筆記) |
| 合格レベル | 3級: 60点以上(100点満点) 2級 :74点以上(123点満点) |
| 受験料 | 3級 :5,500円 2級 :8,000円 2級・3級併願 13,500円 |
食生活アドバイザーの資格取得におすすめな人・おすすめでない人

食生活アドバイザーの資格を取得がオススメなのはこんな方です。
おすすめな人
- 健康のために食の知識をつけたい人
- 家族の健康寿命をのばしたいと思っている人
- 食材の知識を増やし、自信を持って接客・提案がしたい人
- 正しい知識をもってダイエットしたい人
- こどもに安全な食事を提供したい人
- 食育に携わりたい人
一方、次のような方はオススメできません。
おすすめでない人
- 食に興味がない人
- 資格を必ず就職に役立てたい人
- 食の中でも特定の分野だけを極めたい人
食生活アドバイザーの資格をとったからといって必ず就職ができるわけではないので、就職目的での取得はあまりおすすめではありません。また、専門性を極める試験ではないので、食の中でも特定の分野だけの知識をつけたい方には不向きです。
食生活アドバイザーは食の知識を幅広く得ることで、家族の健康管理はもちろん、仕事面でも自信を持って食に関する提案がしたい方にオススメの資格です。
まとめ
今回は、食生活アドバイザーは無駄な資格なのか、就職・生活面それぞれで利用できる資格なのか詳しく解説しました。
- 食生活の知識を幅広く習得でき、食について知るきっかけになる
- 自分・家族の健康管理、ダイエットに役立つ
- 食材の選び方や食品保存方法の正しい知識が身に付く
- 誰でも簡単に受験できるがちゃんと勉強しないと合格できない
- 食生活アドバイザーという職業はなく肩書きを気にする方には不向き
食の知識がつくことで、健康管理ができるようになるのはもちろん、食材選びもたのしくなり、普段の生活にも役立ちますよ。少しでも食に興味がある、食についての広い知識をつけたい方は、ぜひ一度勉強してみてはいかがでしょうか。