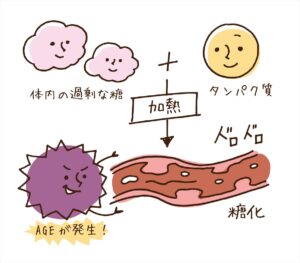お腹がすくけど食欲がわかず、食べられない。お腹も減らないので食べる気力が湧かない。など困っていませんか?
「栄養不足になるかも」「体力がなくなるかも」
食欲がない状態が長く続くといろんな不安を感じてしまいますよね。今回は「食欲がなくなる原因」から、食欲アップにオススメの食材やレシピまで管理栄養士が紹介します。
はじめに結論!
食欲がなくなる原因と対策を以下にまとめました。基本的には食欲がないときでも、量やメニューを工夫したり、完全食を利用するなどして、栄養を補給するようにした方が良いでしょう。
- 食欲がなくなる原因は、体調不良、ストレス、環境の変化など多岐にわたる
- 食欲がなくなると、栄養不足で筋力・体力が落ち、免疫力が低下し病気にかかりやすくなる
- 食欲アップには小分けにして少しだけも食べる習慣をつけたり食事を楽しむ工夫も
- 食欲がない時は消化に良い食事を心がけ、香味野菜を加えたアレンジレシピがGood
- 料理する元気も出ない時は完全食がオススメ
食欲がなくなる原因
そもそも食欲がなくなってしまうのは何が原因なのか。まずはご自身の食欲がない原因を知ることが改善への第一歩です。食欲がなくなる原因は多岐に渡りますが、ここでは主な原因を6つご紹介します。
- 夏バテ
- 具合が悪いとき
- ストレス・精神的な問題
- 薬や病気の治療
- 高齢化
- 環境変化
それぞれについて、詳しく解説します。
夏バテ・脱水症状
暑い時期になるとよく聞く「夏バテ」。暑さや湿度の高い夏の時期に体温調節が難しくなると起きる症状で、疲れやすくなり食欲が低下していきます。

暑い屋外と、エアコンが効いている室内との気温差が激しくなるほど自律神経のバランスが崩れて疲れやダルさが現れて食欲低下に。加えて、汗を大量にかくので体内の水分とミネラル分が失われてしまう脱水症状が起きるとさらに食欲がなくなります。
具合が悪いとき
風邪や発熱で体調が悪いときは体力が消耗してしまい食べる気力がわかない原因の一つ。胃や腸などの消化器系も正常に働かない状態なので、頑張って食べたものの消化が進まずに胃のもたれやさらなる食欲低下につながります。
ストレスや精神的な問題
ストレスや不安などにより、脳が刺激されて摂食中枢が正常に働かずに食欲がなくなります。また自律神経が乱れて胃酸過多など消化器官への負担が増えて食べると胃痛がするなどの症状も。
仕事が忙しいこともストレスの一つ。忙しすぎて食べられない時間が長く続くと胃も小さくなりさらに食欲が落ち込むこともあります。
薬や病気の治療
薬の服用や病気の治療によって、副作用として食欲減退を引き起こすことがあります。食欲がなくなると病気の回復も遅れてしまうため、副作用が出たら医師・薬剤師に相談してください。
高齢化

高齢になるほど食が細くなります。年をとるにつれて体の機能が衰えてくるため、活動量も少ない状態に。筋肉量が減って代謝率が低下します。消化管も衰えて少量しか食べられなかったり、食べたいと思う気力がなくなり食欲減少に繋がります。
環境の変化
引越しや転職など生活環境の変化やライフスタイルを変えたりすると食欲が落ちる場合があります。今まで慣れ親しんでいた場所から新天地に移ったときに落ち着かないと思ったことはありませんか?
実は無意識のうちに緊張して自立神経のバランスが崩れているのが原因。バランスが崩れて食欲が湧いてこなくなるのです。また旅行などでも環境の変化に敏感な方は食欲低下の要因となることがあります。
食欲がなくなる場合のリスク
食欲がないのは体が今危険な状態であるというサインです。食欲がなくなる場合には、さまざまな健康リスクが存在します。
栄養不足と体力・代謝低下
食欲がなくなると十分な栄養がとれなくなり、筋力・体力が低下します。必要な栄養が体に足りない状態が続くとさらに代謝が落ちて食欲がなくなる傾向に。すると体重がみるみる減って栄養失調症になり、体に深刻な影響をおよぼす危険もあります。

食欲がないとき、消化不良や代謝の低下を引き起こしている可能性があります。これにより、エネルギー不足から体が思うように動かずに筋力低下などの身体機能の低下が起こることもあります。
免疫力低下・感染症になりやすくなる
食事からとれる栄養素のビタミンA、ビタミンE、ビタミンC、ビタミンD、亜鉛などには免疫機能を助ける働きがあります。
食事が充分にとれない状態が続くと、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が補われません。すると、みるみる免疫力が低下して抵抗力が弱まり、風邪などの感染症や肺炎などの病気にかかるリスクが高まるのです。
精神的健康への影響
食欲不振はストレスやうつ病と関連があることが明らかとなっています。十分な栄養を摂取できないことが続くと、自律神経系のバランスが崩れて精神的・心理的な健康状態を悪化させることがあります。
食欲を出すためにできる食習慣
食欲がない生活から早く抜け出すためには、健康的な食習慣を取り入れることが重要です。以下におすすめの6つの食習慣を紹介します。
規則正しい生活習慣

「早寝早起きは三文の徳」というように、規則正しい生活習慣を送ることは食欲増加に繋がります。だいたい決まった時間に起きて決まった時間に食事をとるのがベスト。生活習慣を見直すことで、自律神経のバランスがとれて体内時計も整い食欲が促進することがあります。特に、朝食をしっかり摂ると、生活リズムが整いやすいですよ。
栄養バランスがよい食材を食べる
栄養バランスの良い食材は体の回復を早めてくれます。食欲がないときはできるだけ多くの必須栄養素(人が生きるために必要な栄養素)が入っている食品がおすすめ。少量でもしっかり栄養バランスが整います。
食事を楽しむ
食事は義務感で済ませるのではなく楽しむもの。食事を楽しめる心地よい環境を作ることが大切です。好きな食材や調理法を選んだり、お気に入りの音楽をかけたり、おしゃれな食器に料理を盛ってみるのも楽しむことに繋がります。家族や友人と食事の会を設けたり、景色のよい場所で食事をしてみてもよいでしょう。ご自身の楽しめるポイントをぜひ考えてみてください。
小分けで少量ずつ

大量の食事を一度に摂らず、小分けにして摂取することで、胃に負担をかけずに食欲を刺激します。まずはスプーン1杯など一口サイズから始めてみましょう。量を食べられるようになったら徐々に増やしていくのがおすすめですよ。
香りや見た目を重視
食事は、味だけでなく香りや見た目も楽しむもの。香り高い食品や色鮮やかでおしゃれに盛り付けられた料理は視覚や嗅覚が刺激されて食欲を引き起こす助けになりますよ。
また、おいしい食事の匂いによって唾液量も増えるので消化率アップにも繋がります。とくに香味野菜を使うと一層食欲が刺激されるのでおすすめですよ。
水分をしっかり摂取する
体内に水分が不足すると脱水状態となり食欲も低下します。十分に水分をとることで代謝をサポートして食欲が増しますよ。
成人では体内にある水分を汗や尿として1日2.5L分体外に排出しています。つまり一日あたり最低でも2.5L以上の水分を取る必要があるのです。食事が十分にとれないと水分摂取量も少ない傾向にあるので、意識的にこまめに水分をとりましょう。
食欲がない時にオススメの食材やレシピ
食欲がないときにも取り入れやすい食材やおすすめレシピをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
煮込み料理
ポトフやお鍋など野菜が煮込まれている消化によい料理がおすすめです。しっかり煮込むことで繊維が切れて胃や腸の消化を助けます。

ポトフに入れる食材はビタミンが取れる緑黄色野菜がオススメ。炭水化物のごはんを混ぜておじややリゾットにするとエネルギー源も補給できてよいでしょう。タンパク質は衰えた体力の回復に役立ちます。中でも胃に負担がかかりにくい豆腐などの植物性タンパク質をとりましょう。
香味野菜
香味野菜は薬味とも呼ばれ、香りの強い野菜は臭覚を刺激して食欲を増してくれる食材です。料理にトッピングすると味に深みが増したり風味がアップし、食欲増加をサポートしてくれます。
| おもな香味野菜 | 特徴的な香りの成分 | 食欲増進以外の主な効果 |
| 大葉・シソ | ベリルアルデヒド、リモネン | 抗菌・腐敗防止 |
| ミョウガ | アルファピネン | 血行促進、ストレス緩和 |
| ショウガ | ジンゲロール | 血行促進、強壮作用 |
| にんにく | アリシン | 疲労回復、免疫力アップ |
それぞれ特徴的な香り成分も入っており、食欲増進以外の効果も期待できる食材です。独特な香りなので苦手な方も多いですが、もし食べられる香味野菜があれば少しでも良いのでぜひ料理に取り入れてみてください。
おすすめのレシピはこちら。
簡単にできて食べやすいですよ。
和風パスタにも大葉は最適です。
ミョウガの肉巻き。斬新な見た目が面白く食欲をそそります
梅干し・かんきつ類の果物
梅干しやレモン、すだちなどの柑橘類などの酸っぱい食材は、唾液がたくさん出ることで結果的に食欲を増す効果がある食材。酸っぱいものを食べた時に一気に唾液がでた経験はありませんか?これは無条件反射で起きる生理現象。
唾液が出るメリット
- 食べ物の味を感じやすくなる
- 消化を助ける
- 食べ物を飲み込みやすくする
梅干しやかんきつが手に入らない場合は、ポン酢などもおすすめです。ただし酸っぱい食材は食べすぎると胃への負担が大きくなるので、少量を取り入れるのがおすすめです。少しでも食べられると唾液量が増えますよ。
おすすめのレシピはこちら。
梅とそうめんの組み合わせも鉄板です。
梅と豚肉は相性抜群です。
フルーツサンド
フルーツの酸味がきいたフルーツサンドは食欲がない時でも食べやすいですよ。見た目も華やかで食欲をそそります。生クリームが重たく感じられる時はヨーグルトで代用してもOK。さらに酸味が加わりさっぱり食べられる上に、食欲がない時に不足しがちなタンパク質もとれます。

サンドするフルーツは、バナナやモモなどの食感がやわらかいものを選びましょう。繊維質が少ないやわらかいフルーツは消化にも良いですよ。生で食べられる果物はビタミンも豊富に含まれています。さらに最も栄養価が優れている旬の時期のくだものを味わえば、体調が整いやすいですよ。
一気に食べると血糖値が上がりすぎるリスクもあるので、一口サイズに切って少量ずつ食べるのが良いでしょう。
料理する気力がないときにおすすめの食品
おすすめのレシピも紹介しましたが、そもそも食欲がない時は調理や外食自体おっくうですよね。そんな時におすすめな、すぐに食べられる食品をご紹介します。
栄養バランスに優れた完全食(完全栄養食)
完全食は料理をする気力がないときのお助け食品になります!「完全食」とは、一日に人が生きるために必要な栄養素が全て入った食品のこと。食欲がないときに1品で栄養バランスが整った食事がとれます。
完全食は日清食品などの大手企業をはじめ様々な企業が販売しており、食品タイプごとに食事タイプ、スナックタイプ、ドリンクタイプの3種類あります。
手軽に栄養がとれると最近人気がでてきた食品ですが、今や完全食の市場規模は2022年で145億円、2030年には546億円にまで拡大すると予想されており、まさに今後を期待される人気の食品のひとつ!
おすすめの完全食の取り入れ方法
- 3食中の1食を完全食に置き換える
- 他の食事は簡単な副菜だけ
- 固形物が食べられるなら、ベースブレッドが手軽でオススメ
食欲がない時は一日3食すべて完全食に置き換えなくても問題ありません。まずは体力の回復が優先。完全食をうまく使ってできるだけ調理する体力を温存して元気をとりもどしましょう。
手軽に調理できるそうめん
食欲がないときは喉越しよく食べられる麺類、特に「そうめん」はゆで時間が短くて簡単に調理できるのでおすすめ。食欲がない時はエネルギー不足を補うために炭水化物を積極的に食べた方が良いですが、ご飯は喉を通らない方も多いのではないでしょうか?

そうめんは麺類の中でも味のくせが無く、麺も細くてよりすすりやすく食べやすい食材。エネルギー補給にもぴったりです。夏の風物詩のようなイメージですが、冬でも温かい出汁にいれて「にゅうめん」としても楽しめます。
そうめんはアレンジレシピがたくさんあるので、取り入れやすいですよ。
ニンニクも入ってさらに食欲アップ!
あたたかいにゅうめんもおすすめです。
ただし、そうめんは炭水化物以外の栄養が得られにくいので、タンパク質、ビタミンなどがとれる副菜を追加した方がよいでしょう。
まとめ|食欲がない時は食べやすい食事や完全食を!
今回は、食欲がない時におすすめの食習慣や食材・レシピについてご紹介しました。食欲がないからといって食べないままだと栄養不足などのリスクが出てきます。ご自身の食欲がなくなった原因をしっかり理解し、おすすめの食習慣を試してみてくださいね。
料理を作るのが面倒なときは完全食も使いながら、体力を温存して元気をとりもどしましょう!